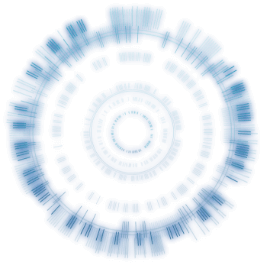EX EPISODE MISSION02
[魔獣追討]
Chapter: 01 夢

男は夢を見ていた。
夢の中で懐かしい記憶を辿り、目に浮かぶのは人生で一番美しいと感じていた時のことだ。
決して長くはないひと時。私はあの子が好きな本を読んで聞かせていた。
かつて世界に溢れていた様々な生命について記した紙の書物。そして、実在しないにも関わらず人々のたくましい想像力のもとでいきいきと描写される空想上の生き物の物語など…あの子は“生き物”のことに大きな興味を示した。
私は何度も読んで聞かせる。何度も望みながらついに授かることのなかった我が子に聞かせるように、あの子に何度も繰り返した。
あの子は純粋だった。私の知る限り誰よりも。
「博士、一番強い生き物は何だと思いますか?」
「どうしてそんなことを聞くんだい?」
男は質問に質問で返す意地悪をした。
「わからないから。わたしに教えてくれるのは博士しかいない」
あの子は再び問い、私は答える。その顔には自然と笑みがこぼれてしまっていた。
他愛もないやりとりだったがこれこそが私が望んでいた、ただ一つのものだった。
「獅子…百獣の王。自分の家族を護る為に戦うんだ」
「では一番恐ろしい生き物は?」あの子は問う。
言葉が出るまでに数秒間。私は口を開いた。
「私が恐れるのは自分こそが生命体の頂点だと考えるような存在……すなわち人間だ」
あの子は納得できていないようだった。人間は弱いと思っている。みんな簡単に死んでいく。そんな光景を何度も見て心を痛めていたからだ。
「たった一つの大切なものを護るために命を懸けられる勇気ある者たちは本当に強い。 だがどんな者でも内に秘めた欲望に飲み込まれてしまう瞬間が確かに存在する。 強力な力を持っているならなおさらだ。そして自分がヒエラルキーの最上位にいると錯誤した 時どうなるか……」
「博士……?」
あの子が不安そうな声で私を呼ぶと私は脳裏に浮かんだ凄惨な光景を打ち消すようにできるだけ明るく振舞った。
「しかし同時に人間が素晴らしい可能性を持った種だと信じているよ。
そして、この星をもう一度生き返らせたいと願う人間がたくさんいるということをどうか覚えておいてほしい」
そう答えた時のあの子のことが思い出せない。
男は目を覚ます。束の間の休息から戦場へと呼び戻される。いつまでも消えない硝煙の香り。ひどく嫌な人間の焼ける匂いが男のするどい嗅覚を刺激する。
千里眼のようによく見える眼が周囲の状況を読み取る。
男が休息してから経過した時間は90分。
男は鋼鉄の騎馬に跨りハンドルを握ると力を込めて愛車に命を吹き込んだ。
髏をかたどったフロントマスクから零れ出す赤黒い励起光 が暗闇を照らす。それは機体中枢へ行くほど輝きを増し、炎のような揺らぎとともに噴出している。力の蓄えは十分だ。
『さぁ行こうか。大切なものは自分の手で守らなければな』

「アナデン」
ここはリバティー・アライアンスやMSGヴァリアントフォースの管理区域から外れた中立地帯の鉱山都市である。
希少な鉱石が採掘できるということで出稼ぎに来る連中が後を絶たない。採掘場は高低差の激しい渓谷の一角にある。周囲は背の高い木々に囲まれ全体で見れば自然が残された場所だが、立体的な地形ゆえに徒歩での移動は困難だった。
採掘救助用ヘキサギア「ウォールバスター」は渓谷の上層で事故に遭ったヘキサギアの救助に向かっていた。ウォールバスターはエアマニューバスラスターを吹かし上空からワイヤーロープを垂らす。
地上で待ち構えていたザック・ザザックはワイヤーロープ先端のフックを手際よく擱座したヘキサギアに繋ぎ、担架に載せた負傷者と共に自身もしっかりと固定する。
「いいぞ、巻き上げろ」
ウォ-ルバスターの操縦席から心配そうに見下ろしているガバナーに、ザックが手振りで指示を送る。
ウインチが巻き上げられていく。
この負傷者を救護所まで輸送して午前の業務は終了だ。
ザックの後ろから若い女性の声が聞こえた。
「親方、お疲れさま」
女の名はキャロル。ザックが娘のように可愛がっているウォールバスターのガバナーである。
時計を見ると休憩にちょうど良い時間だった。
ザックはポケットをまさぐると空のシガレットケースが出てくる。
「ありゃ……空っぽか。悪いがアレを取ってきてくれるか。ついでにみんなにも休んでもらうように言ってくれ」
「了解。親方は先に休んでいてね」
キャロルは自分のリュックを拾うと、救護所になっているプレハブ小屋を勢いよく飛び出し目の前の斜面を滑り降りた。
「お前の義足は耐久性が低いんだ。無茶するなよ」
「分かってるって!じゃあ行ってきまーす」
中層の採掘場に到着すると今日はなんだかいつもより物々しい感じがした
「どうしたの?」
「ああキャロルか、もう昼飯の時間かい?」
鉱山作業員の男は流れる汗を拭うと馴染みの娘に応える。
「ええ。それより何か変な感じ。何があったの?」
キャロルは周囲の男たちから緊張を感じ取っていた。
「この間、南の方でヴァリアントフォースとリバティー・アライアンスの戦闘があったろう。あの時のリバティー・アライアンスの部隊がこの辺りで足止めを食ってて、それで救援を求めてきたらしい」
「ここも巻き込まれるってこと?そんなのやだよ」
キャロルは言う。アナデンはMSGから離れた彼女のような“はぐれ情報体”ですら仲間として迎え入れる懐の深さを持っていた。もっともそれは行き場を失った者たちの寄り集まる闇の暗さでもあり、彼らの中でも思惑の違いから対立することもある。
情報体である彼女は欠損したボディを補修する為に代替品を多数装着しているが、それらは純正部品ではない。本格的な戦闘に巻き込まれたらひとたまりもないだろう。ジェネレーターシャフトのバックアップなど期待できず、記憶や意識を伝送するためのクレイドルもない。情報体といっても物理的に破壊されたらそれまでなのだ。
「大丈夫だ。俺たちだって頭数だけならそれなりにいるんだ。戦闘には加担しないという姿勢で押し切るさ」
男はキャロルにそういうと皆に昼食であることを告げた。